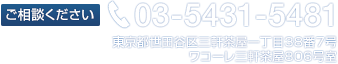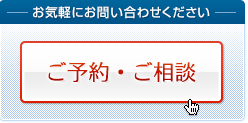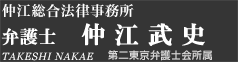一般民事・刑事事件の基礎知識
訴訟に際して収集する主要な証拠および証拠収集手段
はじめに
訴訟(裁判)では、証拠に基づいて当事者の主張する事実が存在するか否かを証明(立証)する必要があります。
最近では、デジタル・フォレンジック(Digital Forensics)と総称される、コンピュータ、スマート・フォン、ICレコーダー等に保存された文字・写真・動画・音声データ等を証拠として収集し、裁判所に提出する手法も重要になってきています。消去されたデジタル・データの復元を専門とする企業もあります。

しかし、必要な証拠は依頼者の手元にあるとは限りません。弁護士は依頼された案件に応じて必要な証拠を行政機関等から収集することになります。
以下に記載した証拠には、依頼者本人が請求して取得することができるものもありますが、弁護士が事件を受任した場合には、弁護士が依頼者に代わって取得する場合がほとんどです。なお、弁護士が依頼者に代わって証拠を取得するにあたり委任状が必要となる場合もあります。
また、弁護士が受任した場合には、以下で述べる『職務上請求』や『弁護士会照会』という証拠収集手段(証拠収集方法)を活用することにより、依頼者本人では取得できない証拠を収集することも可能になります。
1.戸籍謄本、住民票写し
相続人の範囲の調査や訴状の送達先の調査等、弁護士の受任業務の様々な場面で、戸籍謄本や住民票の写しが必要となります。
戸籍謄本や住民票の写しは、プライバシー保護の観点から、第三者による交付請求が制限されており、誰でも請求できるわけではありません。
弁護士には、 『職務上請求』 という手段が認められており、①裁判手続又は裁判外における紛争処理手続の代理人や刑事弁護人として請求する場合や、②破産管財人、成年後見人、遺言執行者として請求する場合は、利用目的を示して第三者の戸籍謄本、住民票の写しを取得することができます。
2.不動産登記、商業登記
土地や建物の過去・現在の所有者、抵当権の設定の有無等を知るためには、不動産登記の内容を調べる必要があります。また、株式会社の代表者や本店の所在地を正確に知るためには、商業登記を見る必要があります。
不動産登記、商業登記の登記事項証明書は、誰でも法務局に申請して、手数料を収入印紙で納めることにより取得することができます。郵送やオンラインにより交付を申請することもできます。弁護士は、依頼された案件に必要な範囲でこれらの登記事項証明書を取得することになります。
3.自動車登録事項等証明書
自動車の所有者を調査する場合、自動車登録事項等証明書により自動車の登録情報を確認することになります。自動車登録事項等証明書は、全国の運輸支局又は自動車検査登録事務所で誰でも請求することができます。
交付請求時には、①自動車登録番号(ナンバープレートに記載)と車台番号の明示、②請求の理由(目的)の明示、③請求者の本人確認が必要となります。もっとも、①については、私有地における放置車両の所有者・使用者を確認する場合や、裁判手続の書類として不可欠な場合などの特段の理由がある場合は、自動車登録番号のみで、自動車登録事項等証明書の交付を受けられることがあります。
4.交通事故証明書
交通事故証明書とは、事件発生の日時・場所、当事者の氏名、簡素な事故態様、自賠責保険会社が記載されたものです。
交通事故の発生を警察に届け出ていれば、自動車安全運転センターの窓口又は郵送で発行してもらえます。
交通事故の当事者(加害者・被害者)だけでなく、損害賠償請求権のある親族、保険会社など正当な利益のある人は交付を申請することができます。
5.固定資産評価証明書
固定資産税評価額とは、市町村が不動産にかかる固定資産税を算定する際の基準となる価格です。原則として3年ごとの評価替えで、地価変動の大きい地域では毎年修正率を評価額に適用しています。
固定資産税評価額は、不動産を目的とする訴訟の手数料の算出に必要な訴額や、不動産の民事保全を申し立てる場合の担保額を決定するための基準となります。
固定資産評価証明書は、原則として、当該不動産が存在する市町村(東京23区は都税事務所)に請求することで取得できます。
6.貸金業者の取引履歴
弁護士が個人の債務整理事件を受任すると、貸金業者に対して、受任通知を送り、取引履歴の開示を求めます。
貸金業者には、取引履歴を開示する義務があるとされており、開示された取引履歴は債務者と個々の貸金業者との取引内容を確定する重要な証拠になります。
取引履歴に基づく引き直し計算の結果、利息制限法所定の利率を超過した支払い(いわゆる過払い金)が発見される場合があります。
7.裁判記録の閲覧・謄写
弁護士が、受任事件に関連する過去の訴訟事件等の記録を閲覧・謄写して事件内容を把握することは、重要な証拠収集手段の一つです。
(1)民事事件記録
民事事件の記録は、係属中の事件については当該裁判所の係属部に、確定事件については一審の裁判所に、それぞれ保管されています。
民事訴訟の記録は誰でも閲覧を請求することができます。もっとも、保全、執行、破産等の非公開事件については、当事者及び利害関係人のみが閲覧を請求することができます。東京地裁には記録閲覧室が窓口として設けられています。
これに対して、謄写ができるのは事件の種類を問わず当事者及び利害関係人のみです。謄写は司法協会に請求することになっており、弁護士が請求する場合、代理人としての委任状が必要になります。
(2)家事事件記録
家事事件の記録は、係属中の事件については当該裁判所の係属部に、確定事件については一審の家庭裁判所に、それぞれ保管されています。
家事事件は対審・公開の手続ではないため、記録の閲覧・謄写いずれについても事件関係者のみです。許可が出る場合でもプライバシー保護の観点から、全面的な閲覧・謄写が認められることはほとんどなく、閲覧・謄写の範囲等について制限がされるのが通常です。
東京家裁では、閲覧・謄写いずれを請求する場合でも、係属中の事件は係属部が、確定済みの事件については記録室がそれぞれ窓口となっています。弁護士が請求する場合、代理人としての委任状が必要になります。
(3)刑事事件記録
確定した刑事事件の記録は、第一審の裁判所に対応する検察庁に保管されており、原則として誰でも閲覧できる建前になっています。しかし、訴訟関係人以外の第三者については正当な理由を明らかにしなければ閲覧を拒まれることがほとんどです。弁護士が、民事事件の当事者の代理人として閲覧を請求する場合、委任状が必要となります。当事者が申請し、検察官が必要性を認めた場合は、謄写も認められるのが実務の運用となっています。
刑事弁護人の場合、起訴後第1回公判期日前は、検察官が取調請求する予定の証拠書類・証拠物については、あらかじめ閲覧・謄写することが認められています。
また、当該刑事事件の被害者等又はこれらの者から委託を受けた弁護士は、第1回公判期日後当該刑事事件の終結までの間は、係属裁判所に申出ることで、原則として当該刑事事件の記録の閲覧・謄写が認められます。
8.弁護士会照会
弁護士会照会とは、弁護士が弁護士会を通じて、受任している事件について、行政機関や企業に照会して必要な事項の報告を求めることができる制度です(弁護士法23条の2)。照会先は法律上、報告義務があるとされています。
弁護士会照会により取得できる証拠は多岐にわたりますが、以下では代表的なものを紹介します。
9.証拠保全
証拠保全とは、訴訟の開始前又は開始後に、訴訟における本来の証拠調べの時期まで待っていては、取調べが不能又は困難になる事情のある特定の証拠をあらかじめ調べる手続のことです。
(1)証人が高齢又は重病で余命が保証できない場合、(2)自動車事故・火災現場の現状が維持できない場合、(3)企業の会計帳簿や取引記録に改ざん・廃棄のおそれがある場合、等に、証拠保全を利用してあらかじめ証拠調べをすることになります。特に医療過誤訴訟では、①診療録、②検査結果、③レントゲン写真などが重要な証拠となるため、これらの改ざん・隠匿を理由とした証拠保全が積極的に利用されています。