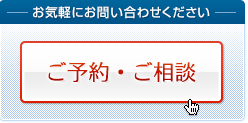一般民事・刑事事件の基礎知識
不当な内容の遺言と遺言無効確認の訴え
はじめに
平成27年1月から相続税の基礎控除額が大幅に引き下げられ、実質的に相続税が増税されたこともあり、相続に対する社会の関心が高まっています。そのため、弁護士その他の専門家に依頼し、遺言書を作成する件数も増えているようです。
しかし、遺言を作成する時点で、遺言者が高齢であるために認知症その他の疾病により遺言の内容・影響を理解しないまま遺言を作成してしまうことや、そのような遺言者の状態を相続人や第三者が悪用し、その者が過大な利益を得ることを内容とした不当な遺言が作成されることがあります。
本稿では、不当な内容の遺言が発見された場合に、その遺言の効力を争うための「遺言無効確認の訴え」 (遺言無効確認訴訟) について説明致します。
1.近時の裁判例
近時の注目される遺言無効確認の訴えの裁判例として、約6億円に上る全財産を顧問弁護士に遺贈する内容の自筆証書遺言の効力が問題となった事件があります。
(1)事案の概要
被相続人(遺言者)Aは、B会社の全株式(「本件株式」といいます。)を保有する、B会社の元経営者で、Xを含む多数の相続人がいました。Aは平成15年12月にB会社の顧問弁護士であるYが自宅に訪問した際、自筆で自筆証書遺言(「本件遺言」といいます。)を作成しました。なお、Aは平成14年頃から認知症の初期症状が始まり、遅くとも平成19年5月にはアルツハイマー病との診断を受けていました。
Yは、昭和40年、昭和60年、平成8年頃にAから民事上の問題について法律相談を受けたことがあり、平成15年5月、Aから公正証書遺言作成の委任状を受領し、また、同年7月には、B会社と法律顧問契約書を交わし、顧問弁護士となりました。Yは平成15年2月から本件遺言書を作成した同年12月までの間に、Aと十数回の面談をし、YはAから平成16年4月、B会社の後継者はCにすることに決め、本件株式はCに譲渡したいと伝えられていました。
本件遺言は、遺産をすべて弁護士Yに遺贈するという内容で、本件遺言によりYが取得したAの全遺産の価格は現金、本件株式などを合わせて合計約6億円にも上ります。
Aは平成21年2月に死亡し、戸籍上法定相続人に該当するXは、弁護士Yを被告として、本件遺言が無効であることの確認を求め、訴訟を提起しました。
一審はAの遺言能力を否定し、本件遺言を無効としました。これに対して、控訴審はAの遺言能力を認めましたが、公序良俗に反するとして、本件遺言を無効と判断しました。
(2)一審(京都地裁平成25年4月11日判決)の判断
- 意思表示を有効に行うための精神能力は「意思能力」と呼ばれ、遺言を行うのに要求される精神能力は特に「遺言能力」とも呼ばれる。意思表示に、どの程度の精神能力が必要であるかは、画一的に決めることはできず、意思表示の種別や内容によって異なる(意思能力の相対性)。
- Aは、本件遺言作成の当時、既に、アルツハイマー型認知症を発症しており、初期認知症の段階にあった。初期認知症の状態の者について、一律に意思能力・遺言能力が否定されるわけではない。しかしながら、本件遺言は文面こそ単純ではあるが、数億円の財産を無償で他人に移転させるというものであり、本件遺言がもたらす結果が重大であること、B会社の経営にもたらす影響はかなり複雑であるとの事情を考慮するならば、本件遺言に関する遺言能力は、小学校高学年レベルの精神能力よりも、もう少し高い精神能力(ここでは仮に「ごく常識的な判断力」と表現する)が必要というべきである。
- Aは、Cを後継者にする意図を有していたのであり、YにB会社の経営者になって欲しくて本件遺言をしたのではない。ところが、Aは、Cを後継者にするには不都合な遺言をしているのに、全く心配をしていない。したがって、Aは、本件遺言をした場合の利害得失を「ごく常識的な判断力」のレベルでさえ、全く理解していなかったものといえる。
- さらに、B会社は、Aの親戚であるCが経営の片腕となっており、同族的色合いが濃い会社である。それなのに、縁のある親戚に対しては、本件株式はおろか、会社経営の基盤となり得る預金さえも全く遺そうとはせず、赤の他人のYに本件株式を含む全遺産を遺贈しようというのは、Aの生活歴からすれば、いかにも奇異なことである。このことは、Aが、本件遺言がもたらす利害得失を理解する能力が著しく減衰していたことを示す一つの事情となり得る。
- Aが、平成15年12月当時、既に、アルツハイマー型認知症を発症していたことをあわせ考えるならば、本件遺言作成当時、Aは、本件遺言がもたらす結果を理解する精神能力に欠けていたものと認めるのが相当である。 したがって、本件遺言は無効である。
(3)控訴審(大阪高裁平成26年10月30日判決)の判断
2.遺言の無効原因
遺言の一般的な無効原因としては以下のものがあります。不当な遺言の遺言無効を主張する場合は、遺言能力、公序良俗違反が主として問題となるため、これらについては3.以下で裁判例も踏まえて詳述いたします。
(1)方式違反
遺言は効力発生時に遺言者が死亡していることから、遺言が遺言者の真意に基づくことをできるだけ担保するため、民法は遺言の方式を厳格に定めています(民法967条以下)。遺言の方式を遵守していない遺言は、遺言として成立せず、無効となります(民法960条)。
例えば、自筆証書遺言については遺言者本人が全文、日付、氏名を自書しなければなりません。これらの事項が記載されていなかったり、本人の自書でなかったりする場合は方式違反として遺言は無効になります。自書か否かの判断には筆跡鑑定が利用されます。
(2)証人の欠格事由
遺言方式が公正証書遺言や秘密証書遺言である場合、遺言書の作成及び内容が遺言者の真意に基づくことを保証するため、証人の立会いが必要です。判断能力が未熟な者や遺言者と利害関係を有する者は証人として不適切であるため、未成年者や推定相続人及び受遺者など民法が定める一定の者は欠格者として証人になることができません(民法974条)。欠格者が証人となって作成された遺言は、欠格者を除くと法律の要求する員数を満たさない場合は無効となります。
(3)共同遺言
共同遺言とは、2人以上の者が同一の証書でする遺言のことをいい、遺言者相互の意思内容や撤回の自由が制約されるおそれがあることから、禁止されています(民法975条)。裁判例では夫婦共同名義の遺言が争われる事例が多いです。共同遺言に該当する場合、双方の遺言内容に内容上の関連がなく、かつ、両者を容易に切り離すことができる等の例外的な場合を除き、当該遺言は無効となります。
(4)遺言能力
遺言作成時に遺言能力がなければ、当該遺言は無効となります(民法963条)。
民法では、満15歳以上の者は、遺言をすることができ、行為能力に関する規定は適用されないと定められていることから、自己の行為の結果を認識・判断することができる能力(意思能力)があれば、通常遺言能力が認められることになります。もっとも、遺言能力が争われる裁判例では、一般的な意思能力を超えた、遺言の内容を理解する能力の有無が問題となっています。詳細は下記3.で後述いたします。
(5)遺言者の意思に問題がある場合
遺言は意思表示ですから、民法の意思表示に関する規定が適用されます。遺言の内容について重大な錯誤があった場合、遺言は無効となります(民法95条)。
また、無効原因に類似するものとして、詐欺又は強迫により遺言をした場合、遺言は取り消すことができます(民法96条1項)。遺言者の死後は、相続人が遺言者の取消権を承継し、遺言を取り消すことができます。取消により遺言の効力は遡って失われます。
(6)公序良俗違反
遺言も遺言者の意思表示に基づく法律行為ですから、他の法律行為と同様に、社会的妥当性に反する内容の遺言は公序良俗違反として無効になります(民法90条)。特に遺贈の内容、相手方について問題となることが多いです。詳細は下記4.で後述いたします。
(7)後見人の利益を内容とする遺言
後見人である遺言者が、後見の計算が終了する前に、後見人またはその配偶者若しくは直系卑属(子、孫など)の利益となるべき内容の遺言をしたとき、その遺言は無効となります(民法966条1項)。被後見人の遺言に後見人が不当な影響を及ぼすのを阻止し、後見事務を適正にさせるためです。ただし、後見人が遺言者の直系血族、配偶者、兄弟姉妹の場合は除きます(同条2項)。
(8)遺言内容に問題がある場合
遺言の方式は遵守されていても、遺言の内容が、遺言者の真意の解釈によって確定できない場合や、法定された遺言事項に該当しない場合は無効となります。
法定された主な遺言事項としては、認知、推定相続人の排除、相続分の指定、遺産分割方法の指定、遺贈、信託の設定、遺言執行者の指定・委託、遺言の撤回などがあります。
3.遺言能力
高齢者の自筆証書遺言については、遺言能力が争われることが多く、近時の裁判例では、有効と判断された裁判例はほとんどなく、無効となっているものが多数です。
遺言能力が認められるためには、意思能力、すなわち自己の行為の結果を認識・判断することができる能力があれば足りるというが遺言能力に関する伝統的な見解です。しかし、近時の裁判例では、遺言能力について遺言事項を具体的に決定する能力、遺言の意味、内容、その重大な効果を理解する能力、等と表現するものがあります。また前掲裁判例の一審(京都地裁平成25年4月11日)では、遺言能力は意思能力の意味であるとしつつも、意思能力は意思表示の種別や内容によって異なるとし、控訴審(大阪高裁平成26年10月30日)もほぼ同様に、遺言の内容、効果を理解する意思能力が必要であり、それは遺言の内容や遺言者の心身の状況等から個別具体的に判断すべきとしています。
このように、遺言では、遺言内容により相対的に判断するのが近時の裁判例の傾向になっています。その判断に当たっては、①遺言当時の遺言者の病状等の精神状態、②遺言者以外の者の介入の影響、③遺言を作成又は撤回するに至った事情・動機、④遺言内容の重要性や合理性などが考慮されています。また、①に関連して医師の判断・所見が考慮される場合もありますが、絶対的な基準ではありません。
4.公序良俗違反
公序良俗違反による遺言無効は、伝統的には、不倫関係の相手方への遺贈が典型的な問題となってきました。この問題については、最高裁の判例(最一小判昭和61年11月20日)があり、当事者の関係、遺言の内容から見て、①遺贈の目的が不倫な関係の維持継続のためか相手方の生活保全のためか、②遺贈が相続人の生活基盤を脅かさないかということが考慮され、公序良俗違反にあたるかが判断されます。
これに対し、前掲裁判例の控訴審(大阪高裁平成26年10月30日)では、弁護士への約6億円の遺贈を内容とする遺言が公序良俗違反にあたるかが、問題となりました。この判決では、①遺言者は、アルツハイマーの初期症状が始まり、親族と疎遠であった状況で相談していた弁護士Yの影響を受けやすい状況にあったこと、②Yが、弁護士として遺言の内容について適切に指導助言するべき立場にあったのに怠り、かえって誘導とも思える積極的な行為に及んで作成に関与したこと、③単なる弁護士と依頼者の関係にも関わらず5億円以上もの合理性を欠く利益を得ていることなどが考慮され、「弁護士が社会正義の実現を使命とし、誠実義務及び高い品性の保持が強く求められている(弁護士法1条、2条)にもかかわらず、高齢及びアルツハイマー病のため判断能力が低下するなどしていたAの信頼を利用して、合理性を欠く不当な利益を得るという私益を図ったというほかないのであるから、全体として公序良俗違反として民法90条により無効」となると判断されました。
遺言の内容だけでなく、弁護士の公的な職務や遺言作成への影響力など、不倫関係に関する裁判例とは異なった観点から当事者の人的属性・関係を考慮している点が注目される判断といえます。
5.不当な遺言を争う法的手続
(1)遺留分減殺請求
不当な遺言がなされた場合、これに不服がある相続人が、まず考えるべき法的手段は遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)です。
遺留分(いりゅうぶん)とは、被相続人の生前の贈与又は遺贈の効果を一部制限して、一定の範囲の相続人(配偶者、子、直系尊属)に一定額の財産を最低限の取り分として保証する民法の制度です(民法1028条)。そして、遺留分として定められた範囲を侵害された相続人は、贈与又は遺贈を受けた者に対して遺留分侵害の限度で財産の返還を請求することができます(民法1031条)。これを遺留分減殺請求といいます。
遺留分減殺請求により返還を求めることができるのは、法定された遺留分の範囲に限られますが、遺言の無効を争うことなく、一定の範囲の財産を相続することが保証されることになります。
ただし、遺言者の兄弟姉妹である法定相続人には、遺留分は認められません。
また、遺留分減殺請求は、相続開始及び減殺すべき贈与又は遺贈のあったことを知ったときから1年又は相続開始のときから10年を経過したときは、行使することができなくなることにも注意が必要です(民法1042条)。このような期間制限の関係から、後の争いを避けるため、内容証明郵便により請求することが望ましいです。
(2)遺言無効確認の家事調停
遺留分が保証されてもなお、遺言が不当であると考える場合や遺留分減殺請求がそもそも行使できない場合は、当該遺言の無効を調停・訴訟で争うことになります。
遺言無効確認事件は、家事調停の対象となる事件ですから、遺言無効確認訴訟を提起する前に、家庭裁判所に対して、遺言無効確認調停又は遺産分割調停を申し立てる必要があります(調停前置主義)。もっとも、調停を先に申し立てなかったとしても、遺言無効確認訴訟が却下されるわけではなく、裁判所が職権で調停に付すことになります(同条2項)。
家事調停では、非公開の場で、家事審判官(裁判官)と民間から選ばれた調停委員が当事者の間に入り、中立的な立場でそれぞれの言い分を聴きながら、話合いによって解決を図ることになります。
(3)遺言無効確認の訴え
家事調停の中で、相手方が遺言の有効性を強く主張して譲歩せず、話合いによって争いが解決できなかった場合、遺言無効確認の訴えを提起することになります。
遺言無効確認の訴えは、遺言の無効を主張する相続人が単独で原告となって訴えを提起することができます。遺言が有効であると主張する相続人や受遺者が被告となりますが、遺言執行者の指定がある場合は、遺言執行者を被告とすることができます。
(4)立証責任
判例によると、自筆証書遺言の無効確認を求める訴訟においては、当該遺言証書の成立要件、すなわちそれが民法の定める方式に従って作成されたものであることを、遺言が有効であると主張する被告側において主張・立証する責任があることになっています(最一小判昭和62年10月8日判決)。例えば、遺言者本人の自書(筆跡)であることは被告が立証することになります。
公正証書遺言についても、同様に民法の定める方式に従って作成されたことを被告が立証することになります。
これに対して、原告側は、遺言能力を欠いていたこと、公序良俗違反すること、証人に欠格事由があること等遺言の方式違反以外の無効事由について主張・立証責任を負うことになります。