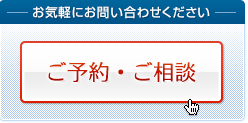一般企業法務の基礎知識
国際契約における準拠法の選択の自由とその限界
1.準拠法とは
例えば、日本企業がフランス在住の中国人からゴッホの絵画を購入したところ、絵画に隠れた瑕疵(欠陥)があった場合、日本企業は中国人に対して日本の民法570条に定める瑕疵担保責任(契約の解除、損害賠償請求)を追求できるでしょうか。
国際契約を締結する場合、当該契約(法律行為)にどの国(州)の法律が適用されるのかが問題となります。当該契約に適用される法律を「準拠法」(Governing Law)といい、準拠法を決定するルールを国際私法(Private International Law)または抵触法(Conflict of Laws)といいます。ある法律行為を国際的に行った場合、準拠法が定まっていないと、当該法律行為の成立の可否も不明となり、また当事者間での紛争を解決するために適用すべき法律が定まらない事態に陥ります。このような事態を回避するために、契約締結の成立および効力について、どの国(州)の法律が適用されるかを明らかにする必要があります。
なお、以下の議論は、日本の裁判所に訴訟が提起されることを前提としています。冒頭の例で、フランスの裁判所に訴訟が提起された場合には、フランスにおける国際私法によって準拠法が決定されることになります。契約の当事者がどの国の裁判所に訴訟を提起することができるのかについては、別途「国際裁判管轄」(民事訴訟法第3条の2から第3条の12参照)の問題を検討する必要があります。
2.国際私法に関する国内規定
我が国において、国際契約に関する準拠法の指定は、平成19年の改正まで、明治31年に施行された「法例(明治31年法律第10号)」という名称の法律の7条から9条において規定されてきました。
その内容は、法律行為の成立・効力の準拠法は、当事者意思によって定められる準拠法によるとし(法例7条1項)、準拠法についての当事者意思が明らかでないときには、契約締結をした場所(以下「行為地」といいます。)の法律によるというものでした(法例7条2項)。
しかしながら、法律行為の行為地は、当事者の意思とは関係なく偶然的に決定する場合があり、またインターネット取引等が発達した現代では、当該行為地が常に明確になっているとはいえない場合も多々あります。このような社会状況において、他の事情を考慮することなく一律に行為地法を準拠法とする法例7条2項の規定は、硬直的すぎるとして、長年問題視されてきました。
そして、平成18年6月、法例における準拠法ルールを大幅に改正した「法の適用に関する通則法」(以下「通則法」といいます。)が制定され、平成19年1月1日施行されました。
3.通則法における準拠法規定の概要
通則法は、行為能力、成年後見、法律行為、婚姻・離婚、相続のように、個々の法律関係ごとに、準拠法について規定をしています。法律行為(契約)については、7条から12条に規定されており、契約の成立、効力および方式についての準拠法指定のルールは、7条から10条を原則規定として、11条および12条が特例として機能します。
通則法は、法例と同様に、法律行為の成立と効力発生は、当事者が当該行為当時に選択した地の法を適用するという、準拠法の指定についての当事者自治を原則としています(通則法7条)。一方で、そのほかの点では大幅に準拠法指定のルールが変更され、準拠法についての当事者自治には限界があります。主要な改正点は以下の4点です。
(1)法律行為の成立と効力について、当事者が準拠法を指定していない場合には、準拠法は「最密接関係地法」によること(通則法8条1項)
法例7条2項が、当事者意思が明らかでない場合には行為地法を準拠法とするとしていた規定内容が変更され、法律行為時における当該法律行為に最も関係の深い地(最密接関係地、the law of the place with which the act is most closely connected)を準拠法とするという規定になっています。「最密接関係地」をどのように決定するかについては、通則法8条2項および3項の推定規定に該当しない場合には、解釈問題となります。
(2)原則として、法律行為において特徴的な給付を当事者の一方のみが行うものであるときは、その給付を行う当事者の常居所地が「最密接関係地」と推定され(通則法8条2項)、不動産を目的物とする法律行為の場合は、不動産の所在地法が最密接関係地法と推定されること(通則法8条3項)
「法律行為において特徴的な給付(Characteristic Performance)を当事者の一方のみが行うものであるとき」とは、たとえば売買契約(車の売買を例にします)の場合がこれに該当します。売主は車の引き渡し義務を負い、買主は代金を支払う義務を負うので、給付行為自体は両者ともに行いますが、当該契約の特徴、つまり他の契約と区別する基準となるのは「車」の引き渡しという点にあるため、この場合、売主のみが特徴的給付を行うことになり、8条2項に該当する契約とされるのです。したがって、この場合、車の給付を行う売主の常居所地法(the law of the habitual residence)が「最密接関係地法」と推定されます。常居所地とは、定義が国際的に確立しているわけではありませんが、一般的には、当事者の意思は必要なく、相当期間居住し、現実に生活している場所を指すといわれています。
(3)当事者は法律行為の準拠法を変更することができるが、第三者の権利を害することはできず(通則法9条)、当該変更は法律行為の方式上の有効・無効には影響しないこと(通則法10条1項括弧書き)
準拠法の変更が第三者の権利を害するとは、変更前には第三者が主張できた事由について、変更後の準拠法に従うと主張することができない場合を指します。この場合、当事者間の準拠法変更は第三者に対抗することができないため、第三者は、変更に関係なく従前の準拠法で認められていた自分の権利を主張することができます(当事者間および利益を害さない他の第三者との関係では、変更は有効です。)。
当事者の準拠法変更が法律行為の方式上の有効・無効に影響しないとは、法律行為の成立時の準拠法により有効に成立した行為が、変更後の準拠法に従うと成立要件を満たしていなかったとしても、当該法律行為が無効となることはないということです。逆に、成立時の準拠法で無効とされた法律行為は、変更後の準拠法によって成立要件を満たしていたとしても、有効とはなりません。
(4)消費者契約・労働契約について、特例を設けたこと(通則法11条、12条)
通則法11条は消費者契約について、同法12条は労働契約について規定しています。通則法が消費者契約および労働契約につき特例を設けたのは、事業者に対して、情報力・交渉力の格差から一般的に弱い立場におかれる消費者および労働者の保護のためです。
4.通則法に基づく契約の準拠法指定の限界
通則法が契約の成立および効力について当事者自治を原則としている以上、国際契約の当事者は、弱者保護や社会経済の秩序維持の観点から各国が規定している強行規定を回避して契約を締結することが可能となります。しかしながら、当該当事者自治には、通則法11条および12条の特例に該当する場合以外にも、限界があります。
(1)絶対的強行規定
絶対的強行規定(Overriding Mandatory Provisions)とは、当事者の準拠法選択の有無および選択した準拠法の強行規定の内容にかかわらず、裁判所が必ず適用しなければならない強行性の高い強行法規のことを指し、通則法11条および12条の強行規定とも区別されます。また、絶対的強行規定の適用について当事者の意思表示は必要ありません。
通則法には絶対的強行規定の適用について明文の規定はありませんが、ある国際契約について紛争が生じた場合に、訴訟が提起された国(州)、つまり法廷地の絶対的強行規定が適用されることについては、争いなく肯定されています。但し、強行規定のうち、いかなる規定が絶対的強行規定にあたるかについて、我が国においては、学説および実務上も共通の理解が形成されているとはいえない状況です。一般的には、独禁法、消費者・労働者保護規定、借地借家法等が絶対的強行規定と考えられています。一方、諸外国においては、絶対的強行規定の適用については、ローマ条約7条、スイス国際私法18条および19条等に規定がありますが、我が国は、絶対的強行規定の適用について規定した国際条約等には参加していません。
したがって、我が国で国際契約についての訴訟が提起された場合に、国内法のいかなる強行法規が絶対的強行規定として適用されるかは、解釈の問題となるので、具体的な個々の事案における裁判所の判断によることになります。
(2)公序(通則法42条)
通則法42条は、外国法が適用される場合に、規定が「公の秩序又は善良の風俗」 (公序、 Public Policy)に反するときは、当該規定を適用しない旨規定しています。したがって、契約当事者が準拠法として日本法以外を選択した場合で、かつ当該準拠法に公序に反する規定が存する場合には、当事者自治が制限され、当該規定は適用されません。通則法42条によって法の適用が排除される場合に、排除後いかなる法が適用されるかについて通則法は規定しておらず、この点については、学説上、様々な見解があり確定しているとはいえないため、解釈の問題になります。
(3)公法
国際私法は、国際契約に適用される私法の決定を取り扱うにとどまり、公法を対象とするものではありません。公法の適用については、当該法律の司法管轄権・執行管轄権の問題を検討する必要があります。例えば、国際契約による物品・役務の提供について日本の消費税法が適用されるのか、国際契約による有価証券の売買に関連して日本の金融商品取引法が適用されるのか、等の問題です。
5.外国法の調査の必要性
以上のように、国際契約には必ずしも指定した国(州)の法律のみが適用される訳ではありません。また、国際契約の内容に、外国所在の不動産の所有権の移転が含まれる場合には、その登記の問題は不動産の所在地の法律により処理されることになり、また合弁会社の設立が含まれる場合には、その設立手続は合弁会社の本店所在地の法律に従うことになります。したがって、国際契約を締結する場合には、指定した国(州)の法律のみならず、当該国際契約が客観的に連結(関連)する国(州)の法律についても調査が必要となります。外国の法律の調査には、外国の法律事務所に別途依頼することが必要になることがあります。