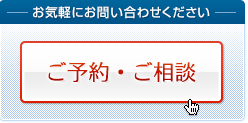労働問題等の基礎知識
みなし残業規定の効力を否定した最高裁判決と対応方法
はじめに
人材派遣会社が派遣社員と締結した、月間総労働時間が140時間から180時間までの場合には月額41万円の基本給のみを支払うと定めた雇用契約の規定について、平成24年3月8日、最高裁判所第一小法廷は、原審である東京高等裁判所の判決を破棄し、当該規定にかかわらず、月間180時間以内の労働時間中の時間外労働についても、基本給とは別に労働基準法第37条第1項(平成20年法律第89号による改正前のもの。以下同じ。)に規定する割増賃金を支払わなければならないと判断し、一部を原審に差し戻しました。これは、従来から「固定残業代」、「定額残業代」、「みなし残業」として論じられてきた問題で、(1) 基本給(固定給)部分に割増賃金が含まれているといえるか、(2) 労働者により時間外手当の放棄がなされたといえるかが問題となります。 本最高裁判決は、労働基準法の規定を厳格に適用することを要求しており、会社・雇用主側に厳しい内容といえます。本稿では、事案の概要と原審及び本最高裁判決の内容を紹介した上で、今後、会社・雇用主の側がどのような点に留意して、雇用契約、就業規則、賃金規程等を作成すべきかについて解説します。

1.事案の概要
2.原審(東京高等裁判所)の判断
原審である東京高等裁判所の本件に対する判断の要旨は以下のとおりであり、本件約定をみなし残業規定として適法有効であることを前提とする判断しています。
3.本件最高裁判決(平成24年3月8日)の判断
これに対し、最高裁は以下の理由により、本件約定のみなし残業規定としての効力を否定し、上記2.の原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとして、破棄しました。
4.本件最高裁判決における櫻井龍子裁判官の補足意見
本件最高裁判決には、櫻井龍子裁判官の補足意見が付されています。櫻井裁判官は、昭和45年に労働省(現厚生労働省)入省後、中小企業労働対策室長、勤労者福祉部長、女性局長等を歴任され、平成13年に退官後、九州大学法学部等で労働法の教鞭を取られ、平成20年に最高裁判事に任官されました。
補足意見の要点は以下の通りです。